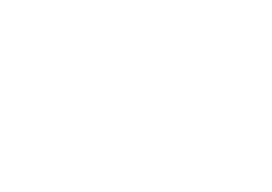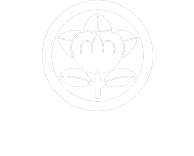ご挨拶

当山は、約500年の歴史を有する曹洞宗の寺院です。
曹洞宗の本山貫首・宗派官長を輩出するなど大本山永平寺(福井県)との縁も深く、長い間修行寺としても利用されていました。また、当山代々の住職が植え継いだ400本もの梅樹が出迎える梅林園の名所としても知られ、早春には芳しい香りが境内を包み込みます。
梅の樹は3月上旬頃に最盛を迎えますが、豊かな自然に囲まれた境内は季節に関係なく四季折々の草花や歴史のうつろいを感じることができます。
ご本尊「千手千眼観世音菩薩」を祀る本堂をはじめ、七堂伽藍の佇まいに和敬静寂の息吹を感じながら、ふとした時に気軽にお立ち寄りいただければ幸いに存じます。
また、日本騎兵の父「秋山好古ゆかりの碑」や片隅にある隠れ茶屋「老楳庵」など、祠や石碑を巡って散策されるのもご一興かと思います。
近年では特に、地域の皆さまの交流の場として種々折々の催事にも力を入れており、県内外はもとより海外からの参詣者も訪れております。
永代供養や墓地分譲など、諸供養に関するご相談も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
成り立ち
今からおよそ560年前-。
宝徳2年(1450年)、「怒仲天誾(じょちゅうてんぎん)禅師」の教えを受け継いだ弟子の「石叟円柱(せきそうえんちゅう)大和尚」がこの地に訪れ、建穂山麗(たきょうさんろく)の「喜慶庵(きけいあん)」に泊まりました。その夜、突如現れた白狐のお告げにより、久住山(くずみやま)の麓に法場(てら)を開くことになりました。
時の守護である「福島伊賀守(ふくしまいがのかみ)」は、深く石叟に帰衣して土地を寄進。この地の石上氏の協力と、石叟の法弟「大巌宗梅(たいがんそうばい)大和尚」も実務をつかさどり享徳元年(1452年)一棟を建立し、伊賀守の法名により「洞慶院(とうけいいん)」と称しました。
石叟は師である恕仲を開山と仰ぎ、自らは二世に居り、大巌を三世としました。大巌は、大いに宗風を挙揚し、賢窓・行之・回夫の三高足を打出しました。この三哲は輪住制(りんじゅうせい)を以て当山に住し、以後末派寺院が一年交替で輪番住職を務めました。
明治の新政で輪番制(りんばんせい)から独住制(どくじゅうせい)に革まり、風外秀吟・普明知常・仏鑑明国・仏山瑞明・仏庵慧明・瑞岳廉芳・鐵山玄道大和尚を経て、現在の住職は大全義裕大和尚に法灯が受け継がれております。
洞慶院のこぼれ話

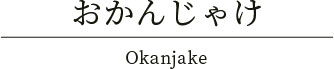
「おかんじゃけ」とは、マダケで作った郷土玩具(おもちゃ)です。
初夏の頃。若竹を二節の長さに切り、一節を金槌や石で叩き潰し、竹の繊維があらわになり糸状になったものを米のとぎ汁で一晩晒して乾燥させ、赤・黄・紫などの色で染めます。
かつて、女の子はこれをクシですき、島田まげや桃割れなどの髪型に結い一種の「おままごと遊び」をし、男の子は「陣取合戦の采配」や「相撲の軍配」にしたといいます。
「おかんじゃけ」と洞慶院の結びつきは文献上つまびらかではありませんが、新竹を利用して作られるので、作る期間は毎年七月十日前後から二十日頃に限られています。
それがたまたま洞慶院の夏祭りである「開山忌(7月19・20日)」の日と一致し、各地からこのおもちゃが縁日にも持ち込まれてきました。
「おとうけんさんの縁日でおかんじゃけを買えば、夏病みをしない」と一種の魔除けや、招福の縁起がもたらされたと言われています。「おかんじゃけ」の故事、由来の口伝は様々であり、製法は同じであっても各地によって呼び名は色々あり約三十種類にも及びます。いずれにしてもこの素朴な民芸品「おかんじゃけ」は、今では全国でこの静岡・羽鳥にしかない珍重な物でございますので、大事に継承していきたいものです。
西国三十三観音巡り

昭和の初め。当時の住職仏庵和尚は、西国巡礼には多大な日数と費用が掛かり徒歩困難な区間もあり、せっかくの信仰の障りとなっているのを歎き、これを洞慶院山内に設置し誰でも容易に巡拝できるようにと発願されました。しかしながら、老師は完成を迎える前に示寂(逝去)されました。
廉芳和尚は先師の遺志を継ぎ、檀信徒の協力を得て、当山の裏山に、順次一体毎に西国三十三所観音霊場のお砂踏の砂を敷き、その上に観世音尊像碑を安置し奉りました。これによって巡拝が楽になり、大慈大悲の観世音の御方便にあずかる事ができるようになりました。お年寄りや、体の不自由の方のため旧正月(2月)の一ヶ月間は、本堂内に特設した三十三番観世音の掛け軸を掲げて礼拝し、集印帳にご朱印を頂くことができます。
洞慶院と「大日本振興力士団」
昭和7年(1932年)1月、幕内力士20名、十両11名が相撲道改革をとなえ、東京品川の中華料理店に立てこもり、協会に対して地位向上や体質改善を要求するストライキ事件が起こりました。
関脇の天竜三郎関(静岡県出身)を中心とした力士たちは、要求の受け入れが認められずとして「振興力士団」を立ち上げ、独自の興業活動などを始めます。洞慶院と「振興力士団」との関係は、主役の一人でもある天竜関が角界入りする前、檀家総代の石上友太郎氏(当時、醤油屋経営)のもとで働いていたというご縁があったことに由来します。また、デビュー当時から懇意にしていたということもあり、仏庵和尚が後援会の会長を引き受けました。そのようなご縁で、「振興力士団」のメンバーがしばらく洞慶院に滞在し、全国各地の巡業に出向くといった時期がありました。やがて、争議事件は収拾されますが、この争議に端を発し現在の力士の在りようや給料制の確立に繋がっていったといわれております。